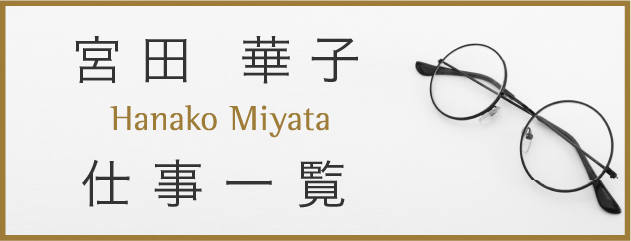© matka All rights reserved.

【朝のコーヒー、午後のお茶】「競売ナンバー49の叫び」を再読
私は漫画は何度も読み直すことがあっても、本を再読することはほぼないです。なのですが、たまに、簡単に読み解くことができない本は時間を置いて再びページを開くことがあります。
現代のアメリカ文学を代表する小説家のひとりである、トマス・ピンチョン の全小説が何冊かづつ発売されはじめた当時(2010年)、私は1作品も読んだことがなかったので、文庫本ですでに発売されていた「 競売ナンバー49の叫び 」を手にとってみました。そして、「う〜ん」となってしまったのです。文体や話の流れは好きなのですが、何を暗示しているのか後ろの本編の1/4はあろうかという「解注」を読みながらの読書はスムーズにはいかず、ようやく読み終えたのでした。
先日、時が経って読み直したときに、「探偵小説」の楽しみと、1964年当時のアメリカの状況にも触れる面白さがありました。この時期、コーヒーと共にゆっくり読み解きながらの読書はいかがでしょうか。と以下は簡単なまとめと感想です。

「競売ナンバー49の叫び」 トマス・ピンチョン
ちくま文庫 1966年 900円
次々と現れる情報と共に、謎解きの旅へ
天才の脳内を凡人が旅することができるとすれば、それは本が一番の媒体だろうと思う。難解な作品で知られるトマス・ピンチョン(アメリカ、1937~)の入門作といわれる、作者が28才の時に書かれた中編小説。これが入門だとしたら、他の作品は一体どうなっているのか…。とはいえ、難解が難解を背負っているような作品でないことは確か。主人公の主婦エディパ(容姿についての記述はないが、おそらくかなりの美女)が死んだ元恋人の大富豪によって「遺産管理執行人」に指名されていたことから、謎に包まれた組織の解明に乗り出す。というストーリー。
謎めいた人々や、演劇、ラッパのマークなどに接するうちに、エディパは混乱していく。この示唆や暗号溢れた文字群を、完璧に理解することは難しいけれど、そもそも、情報エントロピーの増大によって(エントロピーについては小説内でも記載されている)無秩序になっていくことが、この小説の軸と考えると、次々に現れる(時にユーモアのある)断片的な情報(シーン)に身を委ねることができる。表現方法がユニークで、言葉の連続性も面白い。そうして読み進めると、時々ハッとするように、情報社会の現実とつながったりもする。「解注」を見つつ、謎解き読書の旅をどうぞ。

【podcast315】私の日常を彩ってくれた人、ニクヨさん
今年、私の日常をたのしいyoutubeで彩ってくれたのは、以前ポッドキャストで話しました「佐藤ミケーラ倭子さん」とそして今回お話しする「肉乃小路ニクヨさん」でした。在宅仕事のお供に音声だけ聞いてることが多いのですが、話の内容はもちろん、広げ方や収め方、声のトーンなどすごく魅力的ですっかりファンになってしまいました。憧れを込めてあれこれ話してみました。
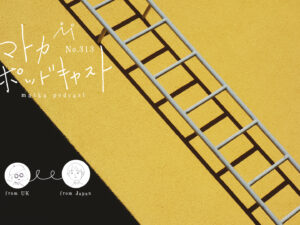
【podcast313】突然のエンドロールに「!?」となる「ハシゴ外され系」映画について
映画館で、終盤「これからどうなるんだろう」と思った矢先、急にエンディングクレジットが流れて「お、終わり?」となった経験はありますでしょうか。そんなエンディングを私は「ハシゴ外され系エンディング」というカテゴリーにしています。そんな映画たちについてあれこれ話しています。
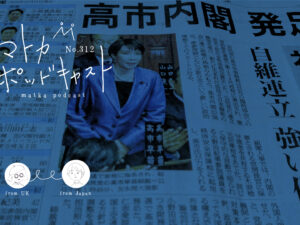
【podcast312】日本初・女性首相誕生→イギリスでの「個人周りの反応」
残念ながら、高市政権が発足してしまいました😿この人だけには首相になってほしくなかったよ…と遠くから😢涙するわたくしフローレンスでございます。

【podcast311】今年は昭和100年と言うけれど…昭和ってかなり酷い
先日、NHKの像の世紀バタフライエフェクト「シリーズ昭和百年(3) 高度成長 やがて悲しき奇跡かな」を視聴して、映像で改めて見ると「昭和って酷いな!」と思わずにはいられませんでした。もちろん映像はある負の部分面を映したに過ぎませんが、「それにしても…」と思ってしまいます。