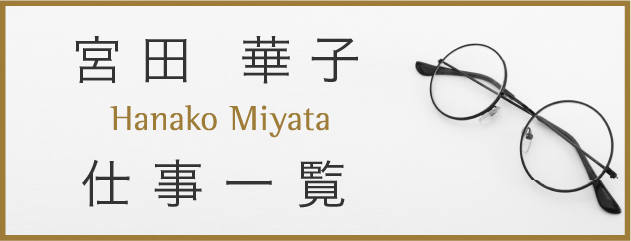© matka All rights reserved.

【写真交換日記194】from London「職人への憧れ」
写真を見て「真紅の紅葉!」と思ったのだけど、糸でできてるなんて!
これは…魂震えますね。
何か密集しているものを見ると心がざわめくワタクシですが、糸が織りなす空間…見てみたかったです。いつか塩田千春さんの展示、私も見る機会があったらいいな。
===
さて、ワタクシも心震える場所に行ってきました。英国伝統のビスポーク(完全オーダーメード)に靴店として世界に名をとどろかせている靴店「John Lobb」です(既製靴も販売している、エルメス・グループの方のJohn Lobbではありません)。ロイヤルワラント(王室御用達)ホルダーとしても知られております。

ここで職人をしている日本人の友人がいるので、実は何度も工房にいれてもらっているのですが、何度来ても独特の雰囲気に見とれ、そして工程を説明してもらうたびにため息が出る思いがします。
全く手を抜くことなく1つ1つの工程を伝統の手法のままやっている。それは「各々の工程が存在する理由があるから」なのだと、当たり前のことを改めて思い知らされます。友人の丁寧な説明で、プロセスがよく分かるのです。

John Lobbの圧倒的に素晴らしい職人技を見て自分のことを考えるのは申し訳ないけれど、ワタクシも手芸が好きで手作業が好きなだけに、技術で勝負する職人に本当に憧れます。そして糸を通したり、ミシンを踏んだり、トンカチで打ち付けたりするその作業をずっとずっと見ていたい…と毎回繰り返し思うのです。

佇まいも素敵です。
どの世界にもその世界にだからこそある厳しさ、辛さ、挑戦があります。私の世界の大変さと靴職人のそれは異なるけれど、細かな1つ1つの作業と技術について聞きながら、日ごろ私が感じている「なかなか先に進めない難しさ」も思い出しました。


工房を案内してもらっていると、かなり興奮しているというのに、何だかとても落ち着いた気持ちにもなります。脳内に革に糸を通したり、ミシンを掛けたりする作業が焼き付き、私も「1つ1つの仕事を明日も頑張ろう」と言う気持になるのです。毎回のことなのですが。


John Lobbのビスポーク靴、私が生涯頑張っても買えなそうです(涙)。でも素敵な靴をいつか買える事を夢見て。

また明日も頑張ります。

【podcast315】私の日常を彩ってくれた人、ニクヨさん
今年、私の日常をたのしいyoutubeで彩ってくれたのは、以前ポッドキャストで話しました「佐藤ミケーラ倭子さん」とそして今回お話しする「肉乃小路ニクヨさん」でした。在宅仕事のお供に音声だけ聞いてることが多いのですが、話の内容はもちろん、広げ方や収め方、声のトーンなどすごく魅力的ですっかりファンになってしまいました。憧れを込めてあれこれ話してみました。
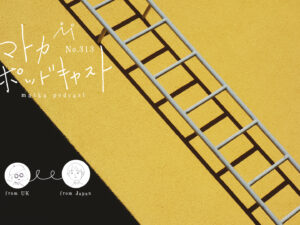
【podcast313】突然のエンドロールに「!?」となる「ハシゴ外され系」映画について
映画館で、終盤「これからどうなるんだろう」と思った矢先、急にエンディングクレジットが流れて「お、終わり?」となった経験はありますでしょうか。そんなエンディングを私は「ハシゴ外され系エンディング」というカテゴリーにしています。そんな映画たちについてあれこれ話しています。
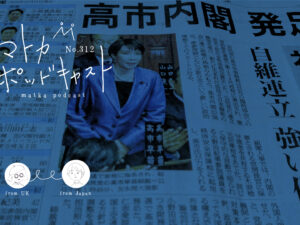
【podcast312】日本初・女性首相誕生→イギリスでの「個人周りの反応」
残念ながら、高市政権が発足してしまいました😿この人だけには首相になってほしくなかったよ…と遠くから😢涙するわたくしフローレンスでございます。

【podcast311】今年は昭和100年と言うけれど…昭和ってかなり酷い
先日、NHKの像の世紀バタフライエフェクト「シリーズ昭和百年(3) 高度成長 やがて悲しき奇跡かな」を視聴して、映像で改めて見ると「昭和って酷いな!」と思わずにはいられませんでした。もちろん映像はある負の部分面を映したに過ぎませんが、「それにしても…」と思ってしまいます。