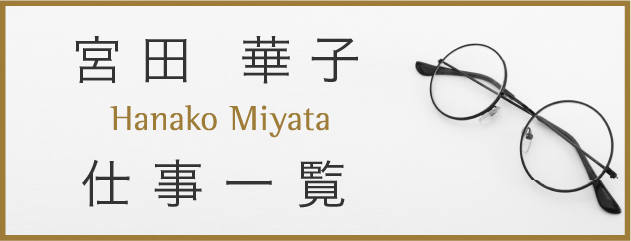© matka All rights reserved.

【ドキュメンタリー】私はイエメンのことを何も知らない BBC『お父さんに誘拐されて(Kidnapped By My Father)』
ドキュメンタリー作品が大好きです。これまでに見て心に残ったドキュメンタリー作品を紹介・記録するアーカイブ。素晴らしすぎて書かずにいられない作品を書き留めます。日本とイギリスの作品が多いですが、国を問わずどん欲に見ています。
4.0 out of 5.0 stars我が家にはテレビがない。以前テレビをもっていたときは、録画済の私好みの「暗めのドキュメンタリー」を再生し、その映像と音を子守唄代わりにして寝る…というのが習慣だった。私は不眠症気味なのだが、これが何だか知らないけどよく眠れたのである。
今の家に引っ越してからテレビを買っていないので、この習慣を忘れ去っていたのだが、あるとき「そっか、スマホやタブレット使えば同じじゃん」ということに気づいた。ここ半年ほどはイギリスのテレビ局提供のアプリを起動し(BBCやChannel4のアプリ)で何かコンテンツを流して、見ながら就寝…というのを習慣にしている。

先日、BBCのドキュメンタリー『お父さんに誘拐されて(Kidnapped By My Father)』(2020年8月12日放送)を就寝前に視聴した。

寝る前に見るにはまあま骨太ドキュメンタリーで、結局最後まで眠らずに見入ってしまった。
主人公はイギリス、ウェールズのカーディフ在住の女性、ジャッキー・サーラさん。1978年、15歳のときに後に夫となるイエメン人の男性サデック(当時28歳)と出会った。そして彼との間に3人の娘をもうける。
夫がDVをするようになり結婚生活が破綻していた1986年のある日、「実家に週末行ってくる」と夫は3人の娘(当時5歳、4歳、18カ月)を連れてでかけていった。そしてそのまま戻ってこなかった…というのが物語の前置きだ。
つまりタイトルのは3人の娘の視点からつけられたもの。ドキュメンタリー自体はジャッキーさんが「母」としての目線で語ることでつづられているので、このタイトルはかなり紛らわしい。
その後娘たちと再会するまでの30年以上に渡る苦悩の戦いについて、彼女自身が語る形式で描かれている。夫は娘を連れ去った後、すぐにサウジアラビアに移住してしまった。しかしパスポートもない18カ月の娘をどうやって海外に連れ出したのか?など謎が多い。インターポールからの情報で、その後元夫と娘たちはイエメンに移住したことまでは分かっていた。ジャッキーさんは大使館や行政、政治家、メディアに訴えまくったが、結局後半は自分一人で闘っていた。
そして2001年初頭のある日、驚く方法で上の娘2人と連絡が取れる。
しかし話はそこでは終わらず、この家族はイエメン内戦(1994年と2015年)によってさらに困難な状況に陥ってしまう。
母がたどった道も、娘たちがたどった道も激動なのだが、彼らの人生に大きく影響を与えたのが、娘たちが住んでいる「イエメン」という国。
「イエメンって…どこ?」っていうところから始まるぐらい、私はこの国のことを何も知らない。
イエメンはサウジアラビアの南に位置する国。ざっと調べただけでもたどった歴史が複雑すぎるので、ひとことで「どんな国」と書けない。
●アラビア半島の南端の位置する、イスラム教国
●オスマン帝国支配→エジプト占領下(19世紀初頭)ののち、1839年に南イエメンをイギリスが、1849年にオスマン帝国が北イエメンを占領。
●第一次世界大戦後、1918年イエメン王国として独立→1962年に王国崩壊。この後南北に再び別れ、内戦。
●1990年、南北が合併してイエメン共和国が成立
●1994年、2015年に内戦
↑参照はこちら。wikiからの拾い読みです。
…う~ん、思い切りざっと書いたつもりでも、全然ざっとにならない複雑さ。
南イエメンはかつてイギリスに占領されていたが、この手の「かつてイギリスに占領されていた」「かつてイギリスの植民地だった」国の話はよく聞く。良い話に使われることもたまにあるが、おおむねそうではない。特に中東におけるイギリスの三枚舌外交については複雑すぎて追いきれていない。
私がこの作品を視聴して最も印象的だったのは、彼女や娘が撮影したイエメンでの映像だ。何気ない家の中の様子から紛争下での日常生活まで、短い映像を見るだけで「同じ時代に生きていても、場所が違うだけで環境も置かれた状況も異なる」ことが如実に分かる。力のある映像だ。
どこに生きているのが「良い」とか「悪い」のではなくて、生きている場所によってさまざまなことが大きく「違う」ということが胸にグサッとくる。
さっきまでイエメンがどこにあるのかもよく分からなかった私なので、他のアラブ国との違いや、紛争の厳しさが分かるわけでは全くない。でも映像で見せられることで、「対岸の火事」はほんの少しだけ近いものになる。
中東についての勉強は全然進んでいなくて、断片をちょこちょこ調べては寄せ集めなのだが、せっかくこのドキュメンタリーを見たので、髙岡豊さんの記事を読むことからもうちょっと突っ込んでみたいなと思っている。
高岡豊さんのことは、大好きなラジオ番組「荻上チキ session-22」で知りました。現在はカレー屋さんの店長さんです。
高岡さんのイエメン関連記事:
イエメン:「無用の長物」と化す「正統政府」(2020/6/22)
イエメン:援助活動も危機(2020/5/27)
おぼえてますか?イエメンのこと(2020/3/28)
イエメン紛争がいまいちわからない理由(2019/9/30)
フーシー派って何?(2017/12/7)
イギリス、特にロンドンに住んでいると、欧州各国が「隣の県」ぐらいの近さなのだが、中東やアフリカも精神的には「同じ国の、ちょっと離れた県」ぐらいの感覚だ。
イギリスにいると言うといまだに「紅茶の国」とか「英国紳士」云々の話をされるが、紅茶は飲むけど別に毎日アフタヌーンティーをしているわけではなく、また英国紳士は「そんな人、どこにもいませんよ」と答えている。どこにいるかも知らない英国紳士より、街を行きかうさまざまな人種・民族を背景に持つ人たちの方がよっぽどリアルなのだが、でも私自身、よくすれ違っている人々の出身国につて詳しく知っているわけでもない。というか、全然知らない。
「全然知らない」という事を、ドッカーんと金づちで頭にぶち込まれた作品だった。
この作品のマトカレート↓

【podcast315】私の日常を彩ってくれた人、ニクヨさん
今年、私の日常をたのしいyoutubeで彩ってくれたのは、以前ポッドキャストで話しました「佐藤ミケーラ倭子さん」とそして今回お話しする「肉乃小路ニクヨさん」でした。在宅仕事のお供に音声だけ聞いてることが多いのですが、話の内容はもちろん、広げ方や収め方、声のトーンなどすごく魅力的ですっかりファンになってしまいました。憧れを込めてあれこれ話してみました。
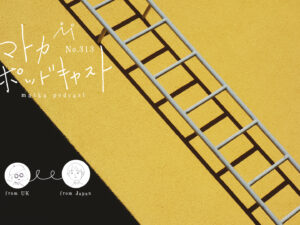
【podcast313】突然のエンドロールに「!?」となる「ハシゴ外され系」映画について
映画館で、終盤「これからどうなるんだろう」と思った矢先、急にエンディングクレジットが流れて「お、終わり?」となった経験はありますでしょうか。そんなエンディングを私は「ハシゴ外され系エンディング」というカテゴリーにしています。そんな映画たちについてあれこれ話しています。
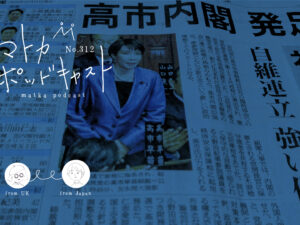
【podcast312】日本初・女性首相誕生→イギリスでの「個人周りの反応」
残念ながら、高市政権が発足してしまいました😿この人だけには首相になってほしくなかったよ…と遠くから😢涙するわたくしフローレンスでございます。

【podcast311】今年は昭和100年と言うけれど…昭和ってかなり酷い
先日、NHKの像の世紀バタフライエフェクト「シリーズ昭和百年(3) 高度成長 やがて悲しき奇跡かな」を視聴して、映像で改めて見ると「昭和って酷いな!」と思わずにはいられませんでした。もちろん映像はある負の部分面を映したに過ぎませんが、「それにしても…」と思ってしまいます。