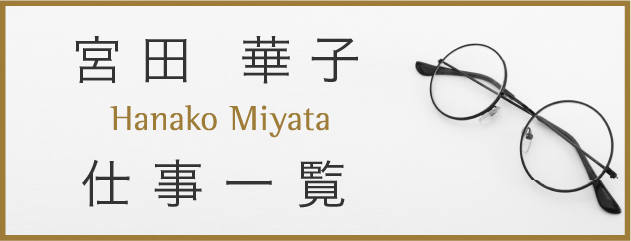© matka All rights reserved.

【ドキュメンタリー(短めレビュー)】私も不登校したかった。:BS1『セルフドキュメンタリー「不登校がやってきた」』を見て思うこと
最近、「セルフドキュメンタリー」がドキュメンタリー界のトレンドなのかな? コロナ禍の影響で撮影が出来なかったこともあると思うけれど。セルフだと、第三者に取材されるより緊張感がないので、意外な言葉がポロリと漏れて面白い。
この番組はTVディレクター&プロデューサー夫婦の家庭をセルフで追ったもの。3人の子供のうち、小学生の次女と長男が不登校に。アニメやイラストを使い、ポップで柔らかな感じで不登校の現状を描いている。
↓NHKサイトからの概要抜粋:
小学4年のわが子が突然不登校になった。学校に行かせるべきか?子供の気持ちを優先し休ませるべきか?私はテレビディレクター。一体どうするのが正しいのか。みずからカメラを持ち、子供が通う学校、フリースクールからそして全てを親が教えるホームスクールまで、さまざまな現場を訪ね歩いた。初めて知った“不登校の真実”。揺れ動く親としての思い、刻々と変わる子供と家族の姿。学校とは教育とはその本質に迫るこん身の記録。
NHKオンデマンド https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2021112338SA000/index.html?capid=sns002
2021年2月23日放送
(C)NHK/ドキュメンタリージャパン
視聴しながら、私の暗黒時代(小学校~25歳ぐらいまではずっと暗黒なんだけどさ)を思い出し、「私も不登校したかったなあ」と思った。私はおっそろしく悩み深い子供だったので、特に小中は学校なんぞに行きたくはなかった。あんな理不尽と差別と偏見にまみれた中に毎日行きたくはなかった。
でもド田舎で暮らしていたし子供に人権なんかなかったので、そんな要求はどうせ言ったって通らないから、ひたずら忍耐の日々だった。
今の子供が抱える問題と、私が子供だったウン十年前とでは状況は異なるので単純比較はできないが、でも、この家庭の場合、両親2人が見識を持ち合わせ、経済的に困っていないインテリ層なことも良い方向に働ていると思う。もし貧困家庭であったり、親がこういったことに興味がなかったとしたら、子供に不登校を言い出す自由があったかは分からない。
子供に選択肢があり、発言する自由がある家庭のドキュメンタリーだったのはとても良かった。次女ちゃんがぽつりぽつりと話す例は胸が痛かったけれど、それでも全体的に心穏やかに視聴できた。
長男君もこのままのびのびっと育ってほしいな~。
NHKオンデマンドでの視聴はこちらから。

【podcast315】私の日常を彩ってくれた人、ニクヨさん
今年、私の日常をたのしいyoutubeで彩ってくれたのは、以前ポッドキャストで話しました「佐藤ミケーラ倭子さん」とそして今回お話しする「肉乃小路ニクヨさん」でした。在宅仕事のお供に音声だけ聞いてることが多いのですが、話の内容はもちろん、広げ方や収め方、声のトーンなどすごく魅力的ですっかりファンになってしまいました。憧れを込めてあれこれ話してみました。
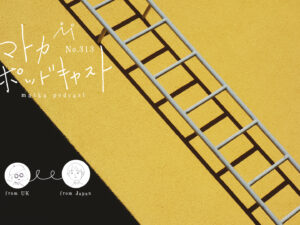
【podcast313】突然のエンドロールに「!?」となる「ハシゴ外され系」映画について
映画館で、終盤「これからどうなるんだろう」と思った矢先、急にエンディングクレジットが流れて「お、終わり?」となった経験はありますでしょうか。そんなエンディングを私は「ハシゴ外され系エンディング」というカテゴリーにしています。そんな映画たちについてあれこれ話しています。
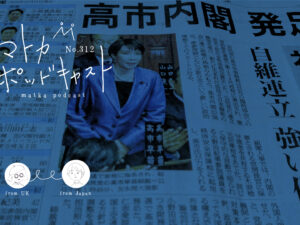
【podcast312】日本初・女性首相誕生→イギリスでの「個人周りの反応」
残念ながら、高市政権が発足してしまいました😿この人だけには首相になってほしくなかったよ…と遠くから😢涙するわたくしフローレンスでございます。

【podcast311】今年は昭和100年と言うけれど…昭和ってかなり酷い
先日、NHKの像の世紀バタフライエフェクト「シリーズ昭和百年(3) 高度成長 やがて悲しき奇跡かな」を視聴して、映像で改めて見ると「昭和って酷いな!」と思わずにはいられませんでした。もちろん映像はある負の部分面を映したに過ぎませんが、「それにしても…」と思ってしまいます。